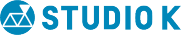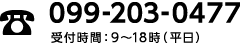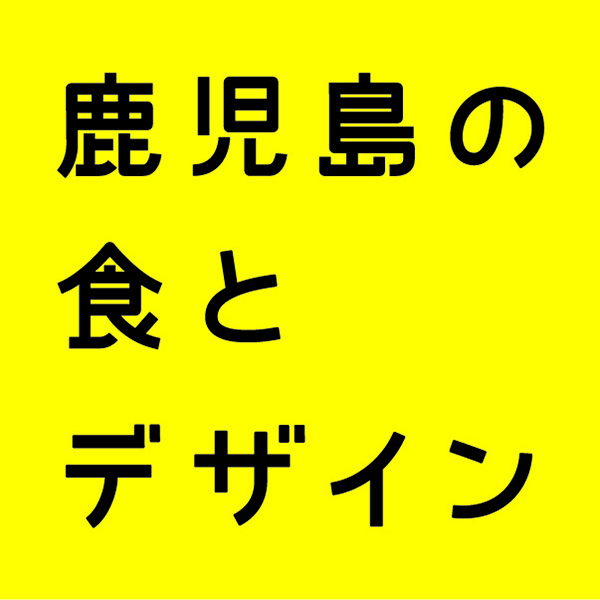より良い関係構築に向けたPR
PR=Public Relations、広報とは。
PRは日本語で「広報」とされ、合わせて広報・PRという言い方がなされます。アメリカの大学の教科書には
組織体とその存続を左右するパブリックとの間に、
相互に利益をもたらす関係性を構築し、維持するマネジメント機能である
と記されているそうで、その組織体には企業・事業者のみならず、官公庁・学校・病院・NPOなどすべての組織について必要な考え方とされています。
そこで広報・PRのマネジメントとは、つまり「関係性を構築し維持するマネジメント」と言うことができ、さらに分解すると、
〇企業・行政・公的機関など社会に存在するあらゆる組織が、
〇利害関係者(ステークホルダー)と双方向のコミュニケーションを行い、
〇自身の組織内に外からの情報をフィードバックして自己修正を図りつつ、
〇パブリックとより良い関係をつくり、継続していくマネジメント
と言い換えることができます。
広報・PRと広告・宣伝の違い
広告・宣伝と広報・PRの違いを説明する言葉にこういう言い方があります。
広告・宣伝は「Buy me、買って!」
広報・PRは「Love me、好きになって!」
広告・宣伝は「短期的な効果を求める西洋医薬」
広報・PRは「じっくり体質改善をめざす漢方薬」
広告・宣伝は「買ってほしいという直接的な働きかけで、テレビや新聞・WEBなどに有料出稿することで自社が言いたいことを言いたい形で直接伝える方法」
広報・PRは「好意的な態度や信頼感を持ってもらうための間接的な働きかけで、購入の前提となるコミュニケーション活動。この1つがパブリシティ」
どちらが良い悪いというものではなく、目的に合わせてコミュニケーションをマネジメントする必要があります。
広報・PRの対象・ステークホルダーとは誰か
ステークホルダーとは、その組織にとって、利益か損失かに関わらず、何らかの影響を企業に及ぼす存在のことを言います。
たとえば・・・。
- 顧客・消費者
- 従業員
- 株主・投資家
- 取引先
- 行政機関
- 地域社会
- 仕入れ先
- 販売代理店
- 業界団体
- 労働組合
- NPO
- NGO
- マスメディア
- SNS含めたWEBメディア
この中のそれぞれとより良い関係構築を目指した情報交換、つまり広報と広聴を行っていくことが必要とされます、
地域企業が取り組む広報・PR
1.まずは広聴、声を集める
広報・PRと広聴は両輪です。お客様、取引先、地域などそれぞれのステークホルダーの方がどのような印象を持っているか、発言をしているかは広報・PR計画の第一歩です。ありがたいことに今はWEB検索やSNS検索で多少の差はあれ集めることができます。また営業担当の方には取引先やお客様からの声が集まっているはずです。
2.広聴した情報を分析し社内の方針と照合
会社には経営方針があります。その経営方針と広聴で得られた結果を合わせてみると、往々にしてギャップが存在しています。たとえば(地元の材料を使っているのに、まったく伝わっていない…)のように。地元の材料を使うという1つの方針を、どのようなメッセージと形で広報・PRしていくか、それが広報・PR計画です。
3.広報・PR計画の実行手段
広報・PR活動はメディア向けのパブリシティに限りません。社内向けには社内報やイベント、メディア向けにはプレスリリースや発表会、地域向けには工場見学会…。計画にもとづいて最適な形=実行手段を組み合わせて実施します。またそれを評価し次につなげ取り組み続けるのが広報・PRです。
中小企業が取り組みやすい5つの広報・PR
- 新商品・サービスのリリース、新店舗のオープン
- 公開型の企業イベント、地域イベント
- ○周年、通算○万人など区切りイベント
- 創立記念日、入社式等のユニークな定例行事
- 地域らしさや歴史性を感じられる情報
「買う」を支える「好感=なんかいい感じ」
昨今「ブランド」の重要性が増しています。類似の商品・サービスが多く存在する中で選んでいただくために、基本的に好意的な感覚・態度が形成されるような、継続的で横断的な取り組みをブランディングといいます。
このブランディングにおいて「なんかいい感じ」という「好感」があることが大きな影響を与えます。いくつもある選択肢から「なんかよくわからないけど、この会社知ってる/ちゃんとしてる」という理由で選択する比率はますます高まっていると言われています。選択肢が多いため「選択疲れ」しているというのです。
この広報・PRは、会社をとりまく関係性をモニタリングし、自社の動きを軌道修正し反映させ、そしてより良い関係性を模索する広報・PRの活動は、今後さらに重要性を増すと考えられています。